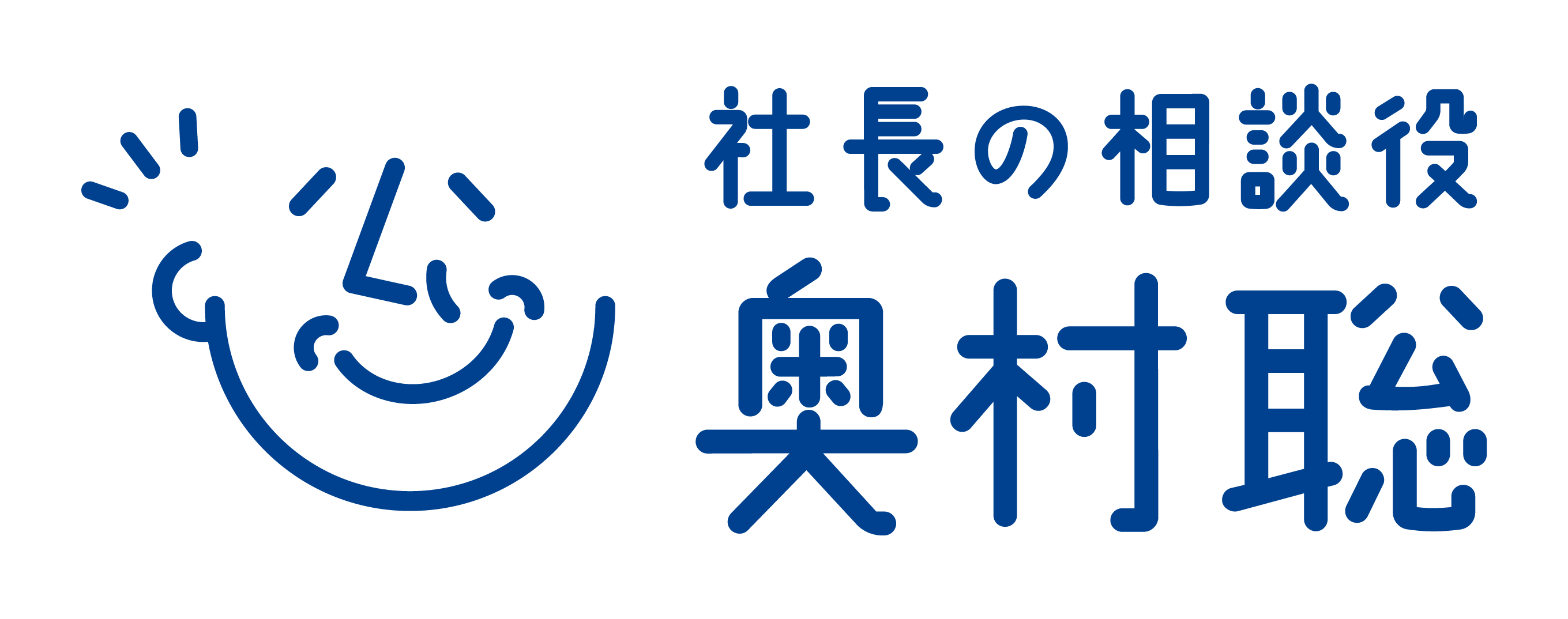継ぎたくない、継がせたくない事業があったら?
会社の中で、いくつかの事業を展開している場合があります。
例えば輸送のビジネスをしている会社は、社内でタクシーとバスの事業を行ていたり。
建築と土木の事業を同じ会社でやっている場合もあります。
普通に事業承継をするならば、これらすべての事業を後継者は継ぐことになります。
しかし、それが不都合な場合もあるのです。
★不採算や後継者の能力的問題・・・
たとえば、利益が出ている事業と不採算の事業が同居している場合はどうでしょうか。
無理にすべてを承継しても、不採算部門に足を引っ張られるのが目に見えます。
逆に採算の取れている事業だけを承継できれば、いいバトンタッチができることでしょう。
事業の収益性には問題がなくても、後継者の考え方や好みの問題があるので、すべての事業が手掛けたいものではない場合があります。
経営能力的にも、すべての事業を回せない場合もあるかもしれません。
「建築の事業はわかるけど、土木のことはわからないから手を引きたい」
こんなパターンです。
いずれの場合も、会社分割や事業譲渡で会社を分けることで、一部の事業だけを承継する道を作ることができます。
会社分割を使った不採算部門を外した事業承継スキーム解説
モデルを使って簡単にスキームを説明します。
まず、A事業とB事業を行っている会社があるとします。
これを事業承継の前準備として分社します。
なお。ここでは会社分割を使う方法をご説明しますが、事業譲渡でも類似のことができます。

会社分割の場合は2パーターンがありえます。
一つは、外に出した会社が子会社となるパターンです。
こちらの場合は、子会社となったB事業を後継者が引継ぐ設計とします。
A事業をやっている元会社から後継者が子会社の株式を引継ぐことで完了です。。

もう一つは、B事業を引き継ぐために新しくできた会社の株式を、これまでの株主が持つパターンです。
先ほどの会社の親子関係と比較すれば、こちらは兄弟関係のようになります。
後継者は株主から株式を譲ってもらうことで、事業承継が達成できます。

商売の様子や引き継がせる資産負債、税金などを考慮して、どの事業を元の会社に残し、どの事業を新会社に持って行くか決めます。
また、親子パターンと兄弟パターンのどちらが適しているかも同様に判断します。
この辺りは分社スキームの肝となり、経験豊富な専門家のアドバイスを受けながらやるべきところでしょう。
事業の定義は任意に考えてOK
このような話をすると「ウチは一つの事業しかやっていないから、会社分割が使えない」と思う方もいらっしゃるはずです。
しかし、ご自身が認識しているよりも、会社はいろんな事業をやっています。
そしてこちらで任意に線を引いて、別の事業とみなしてしまうことが可能なのです。
たとえば、メーカーとして一つのアイテムの製造と販売をやっている会社があったとします。
この場合、製造事業と販売事業と、別の事業をやっていると考えてしまうことだってできます。
ちらかを会社分割で別の会社にしてしまうことができるかもしれません。
もし分けることができれば、後継者は、会社を継ぐ、会社を継がないという選択肢の他に、製造事業だけ(または販売事業だけ)継ぐ、という選択肢を持つことができます。
各地に店舗を展開している会社でもそうです。
東日本と西日本を別の事業とみなし、別の会社にすることだってできます。
分けられるのは2つまでとはいいません。
必要があれば、3つにでも4つにでも会社を分けることができます。
⇒相談申込・お問合せは、こちらへお願いします